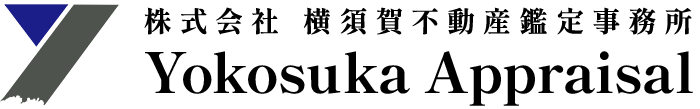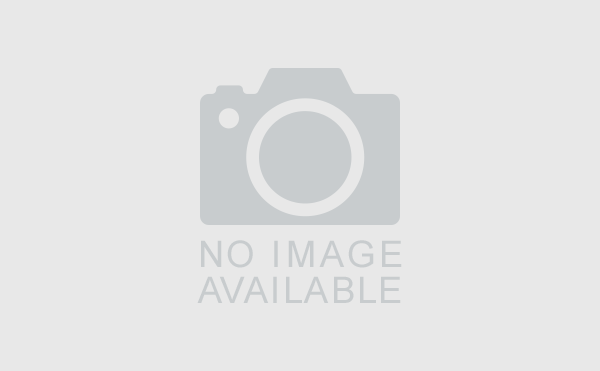継続地代の実態調べ(平成21年における調査結果)
普通借地権の地代水準について
提 供 日税不動産鑑定士会
(社)日本不動産鑑定協会の会員の中で、東京23区内における普通借地権の継続地代の実態を、昭和50年以降3年毎に調査して発表している研究グループがあります。
その研究グループの調査によると、平成21年における調査結果は次のとおりです。
・ 調査範囲 東京23区内
・ 平成21年1月1日現在において授受されている地代
・ 地代の収集事例数 742件
(1)東京23区内地代の水準
| 用 途 別 | 平成21年1月1日現在 | (備考)平成18年1月1日現在 | (備考)平成15年1月1日現在 | |
| 住 宅 用 地 | 1,107円 / 3.3 m2 | 1,123円 / 3.3 m2 | 1,135円 / 3.3 m2 | |
| 非住宅用地 (商業地・商住併用を含む) | 普通 | 1,944円 / 3.3 m2 | 2,064円 / 3.3 m2 | 1,987円 / 3.3 m2 |
| 高度 | 13,480円 / 3.3 m2 | 13,853円 / 3.3 m2 | 12,482円 / 3.3 m2 | |
この表は、東京都23区内の地代収集事例を単に算術平均したものですが、この表で理解されるように、住宅用地の地代が概ねほぼ横這いで推移し、非住宅用地(商業地)の地代も概ね横ばい傾向にあることが伺えます。
(2)地価(更地価格)に対する支払地代年額の割合(「活用利子率」と呼ぶ)
| 用 途 別 | 平成21年1月1日現在 平均的活用利子率 | 平成18年1月1日現在 平均的活用利子率 | (備考)平成15年1月1日現在 平均的活用利子率 |
| 住 宅 用 地 | 7.6 / 1,000(0.76%) | 8.3 / 1,000(0.83%) | 8.0 / 1,000 (0.80%) |
| 非住宅用地 (商業地・商住併用を含む) | 11.1 / 1,000(1.11%) | 14.1 / 1,000(1.41%) | 13.5 / 1,000 (1.35%) |
この表で理解されることは、東京23区において、地価が前回に比し著しく上昇したことを受けて活用利子率が低下したことが伺えます。
すなわち、地代は地価が上下する中でもその相関関係を打ち消して、直接的には地価には左右されていないのが実態といえます。
(3) 地代の公租公課に対する倍率(支払地代年額 /公租公課)
| 用 途 別 | 平成21年度 公租公倍率 | 平成18年度 公租公倍率 | 備 考 |
| 住 宅 用 地 | 4.5倍 | 4.1倍 | 平成7年度第48号東京民事調停協会連合会発行資料によれば、住宅用地の公租公課の倍率は概ね3.1倍前後、非住宅用地(商業地)のそれは2.4倍前後であった。 |
| 非住宅用地 (商業地・商住併用を含む) | 3.9倍 | 4.1倍 |
住宅地については、固定資産税等が課税標準額の特例措置や高負担措置の継続により、この間、地価の変動に関わりなく概ね据え置かれ、一方で地代も横這いのケースが多かったことから、ほぼ公租公課の倍率も同じような結果になったとものと思われるます。
なお、従来の倍率が住宅用地で概ね3.1倍前後、非住宅用地で概ね2.4倍前後であったことは、東京簡裁等の調停成立事例からこれを証することができます。
以上、主な調査結果です。
ところで、地価と地代との間には相関関係があると言われていますが、現実には地代は地価には追随していません。地代はその土地の公租公課に追随して推移するとされています。しかし、公租公課も行政的要因によって増徴されたり、減額されたりしますので、その関係も直接的には維持されなくなってきているといえます。
特に、地価の上下が激しい昨今においては、地価の下落から上昇に転じた後になって、以前の地価下落を反映した評価に基づく固定資産税等が下がったり、金融危機以降の景気低迷を受けて、地価が下落している最中に、それ以前のミニバブルによる地価上昇を反映した評価に基づく固定資産税等が上がってしまうという、非常に分かりにくい状況になっています。
今回の調査からは今のところ地代は殆んどが横ばいの推移であるといえますが、今後は、全体的に地価が下落する中で、固定資産税が上昇していく可能性があり、地代の二大指数が相反する方向に進んでしまうという状況が続くことになると予測されます。
このため、今後どのように地代が推移していくのか、注視していきたいと思います。
ただ、地代市場の閉鎖性は想像以上のものがあり、大きな動きはなかなか生じないのではないかとの考えもありますが、果たしてどうなることでしょう?
(文責 横須賀博・林達郎)